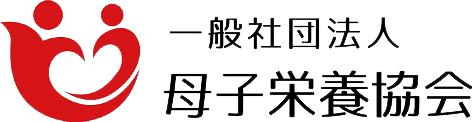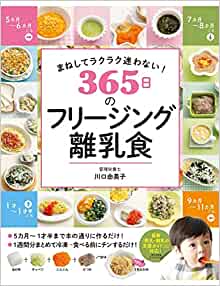離乳食の完了はいつ?母乳やミルクをやめる?
離乳食、いつまで続くの?幼児食はいつから?と困ってしまうことはありませんか?
そんな時に考えたいのは、離乳食は何なのかという離乳食の言葉の定義です。
それがわかると、食べさせるものを少し悩まずに済むかもしれません。
回答は「離乳食の完了とは何カ月です!」というようなものではありません。
そのようなものがないのが食事の良さでもありますね。では、まず離乳食についての基本をみていきましょう。
離乳食は何のために食べるの?
離乳食とは、成長に伴い母乳又は育児用ミルク等の乳汁だけでは不足してくるエネルギーや栄養素を補完するために、乳汁から幼児食に移行する過程(=離乳期)*1)に与えられる食事をさします*1)。
つまり、エネルギー(カロリー)をおもに母乳やミルクで補ってきた赤ちゃんが、成長に従ってごはんで補っていく過程のようなものなのですね。

離乳食の完了は、大人と同じになるわけではありません
離乳食とはやわらかいもので塩分を気を付けるものであると思っている方も多いかもしれませんが、幼児食というカテゴリーに属したとしても、ある程度お子さんの咀嚼への配慮は必要です。
たとえば指でつぶせないくらいの硬くて小さい豆のようなものはあげないようにします。
これは幼児食でも一緒です。大きさなども何かが変わるというわけではありません。
ペットボトルの蓋くらいの大きさで丸くて硬いものなどは、
誤嚥の可能性もあるので、薄くきるなどの配慮はしばらく必要になるというわけです。

離乳食と幼児食の違い
市販の本などは、「離乳食」「幼児食」とわけられていたりします。筆者も離乳食や幼児食の本を書いています。
しかしながら、その線引きや区別はとても曖昧なもので、何歳だからこうしましょう というようなものは特段ありません。
強いて言うなら、
・離乳食はエネルギー比率として若干の母乳やミルクの量も考える
・幼児食はエネルギーをすべて食事からだけで考える
という違いはあります。

管理栄養士
つまり幼児食とは「食べる量が多くなるでしょう。」くらいの意味です。
もちろんレシピは「一般的な量」ですので、
私たちが大人のレシピをみてこれでは足りない/これでは多い と感じるように、
お子さんによって多かったり少なかったりすることもあるかと思いますので、臨機応変に量は変えて構いません。
離乳食はいつまで?離乳食の完了とは?
授乳・離乳の支援ガイドでは、「離乳完了期は12-18ヶ月頃」とされています。では、このあとはどうしたらいいのでしょうか。
また、いつが離乳食の完了なのでしょうか。
よくあるご質問「離乳食の完了とはいつ?」
まず、基本として、母乳やミルクをやめる、断乳・卒乳などと、離乳は別問題となります。
離乳とは、おもに食事で栄養がとれるようになるまでの過程のことになりますので、
母乳をやめる必要はありません。
離乳食の完了とは、形のある食物をかみつぶすことができるようになり、
エネルギーや栄養素の大部分が母乳又は育児用ミルク以外の食物から摂取できるようになった状態をさします。
母乳やミルクをやめる必要はありませんが、回数はかなり減っている頃ではあり、
エネルギー(カロリー)のほとんどは食事になってくると覚えておくといいでしょう。
これがだいたい1歳~1歳半となります。その時期は1歳半だから終わり!というようにきっぱりと決められるものではありません。
離乳食完了期から幼児食への移行は?
離乳食完了期(=離乳完了期)から幼児食への移行というのは、決まりは全くありません。
例えば食事の形状が何ミリから何ミリに変わるわけでもありません。しばらくは、大人の親指と人差し指の爪でつぶれるくらいの硬さのものがいいでしょう。
ただ食事の量は変わっていきます。母乳やミルクの量が少しずつ減っていくのと同時にからだも大きくなり、運動量も増えるので食べる量も増えることでしょう。
母乳やミルクは牛乳に変えず食事で補う
大切なことは、離乳の完了時期とは「母乳やミルクで補っていた栄養を、食事で補っているのだ」という認識をもつことです。
例えば母乳やミルクの栄養を牛乳に変えてしまったりすると、その量によっては牛乳貧血などの心配もまだありますし、簡単に飲めることから栄養バランスの方よりも気になります。
あくまでも母乳やミルクの代わりは「食事」です。これが幼児食となります。
ごはん、おかずを食べることが大切です。あまりg数にこだわらず、ごはんは?野菜は?タンパク質は?となんとなくのバランスを考えながら続けやすい食生活を、各家庭に応じて考えていきたいですね。
【関連記事】授乳・離乳の支援ガイド(厚生労働省 2019年改定)
参考文献
*1)厚生労働省研究班「授乳・離乳の支援ガイド2019年改定」P.29,2009
著者執筆の記事一覧
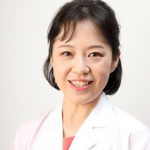
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
著者の記事
- 2024年7月16日コラム切り干し大根、栄養価が高いって本当?
- 2024年7月12日コラム離乳食冷凍小分けトレー(フリージング用容器)の使い方と注意点
- 2024年6月18日コラムしらすを離乳食に使う時、塩抜きしたほうがいい?いつまで?
- 2024年6月14日コラム保育園など児童福祉施設における食事の提供ガイド、改訂からみる現状の問題点と今後の課題点