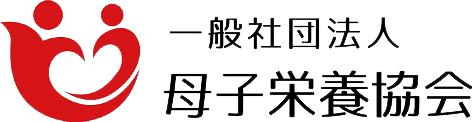ベビーフードは無添加やオーガニック、有機野菜がいい?
ベビーフードは無添加がいいのでしょうか?
情報や企業の宣伝に惑わされないように賢い消費者になるためには、
無添加とはどういうものなのか、
オーガニックとはどういうことを指すのか、考えてみましょう。
ベビーフードは上手に使えば安心

「離乳食を作るのが大変だからベビーフードだけでいい!」という方もいらっしゃいますよね。
それが、ママパパが笑顔になれる方法であるなら、ベビーフードはとても良いでしょう。
しかしながら、高価ですのでベビーフードばかりを食べさせるのは経済的にも大変かもしれませんね。
意外と離乳食は、茹でるだけ、電子レンジで加熱しただけなどでも食べられるものはたくさんあります。もしできたら、赤ちゃんが生まれたことをきっかけに、少しだけ料理に興味を持ってみていただけると嬉しいです。

管理栄養士
たとえば、じゃがいもなどは皮ごとラップにつつんで、
電子レンジで1個あたり4分ほど加熱してから皮をむいてつぶせば、
赤ちゃんでも食べられます!
「旬の食材って茹でるだけでもおいしいな」というような経験ができると、今後続いていく家族の食事が少し変わるかもしれません。
でも、離乳食づくりのために頑張りすぎる必要はありません。

管理栄養士
ベビーフードを上手にとりいれつつ、手作りもできるところから楽しみましょう。
ベビーフードの選び方
たくさんの種類があるベビーフードは、それぞれ用途にあわせて使い分けできます。
レトルト、瓶詰、乾燥品、冷凍などがあるので、使用シーンによって使い分けるといいでしょう。

ベビーフードの種類
ベビーフードは主に、レトルト、瓶詰、乾燥品(フリーズドライ、ドラムドライ)、冷凍 などがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。
レトルト・瓶詰
メリット:そのまま食べられる 、種類が豊富
デメリット:食材の味がわかりにくい、柔らかすぎることがある
乾燥品
メリット:軽い、持ち運びに便利
デメリット:お湯が必要
冷凍
メリット:食材の味などがわかりやすい
デメリット:加熱が必要、単品食材の者が多い、冷凍庫保存必須
ベビーフードに含まれる添加物
日本でベビーフードとして売られているものは、添加物の心配はほとんどありません。
そもそも、日本でリスト化されている、
使用して良い食品添加物は、危険なものではないからです。
もちろん添加物の原料そのものをごくごくと毎日たくさん飲めば、
なんらかの健康被害はあるかもしれませんが、食品につかっても良い基準はごくわずかであり、
人間が一生食べても大丈夫な量よりもかなり低い水準で作られています。
添加物の基準
日本では、危険な食品添加物が使われないように、
食品衛生法(厚生労働省)で定められます。
それとは別に、ベビーフード協議会に入っている6社(アサヒグループ食品和光堂、江崎グリコ、キューピー、ピジョン、森永乳業、ビーンスターク)では、独自にさらに厳しい自主規格をもうけています*。
基本的には、食品を安全に保つことに必要なもの以外の添加物は使われていませんので、
安心して食べられると考えていいでしょう。

管理栄養士
でも、添加物が入っているものはやっぱり子どもにはあげたくないです

管理栄養士
添加物とひとくくりにしないようにしたいですね。例えば、豆腐のにがりなども添加物です。
豆腐は、添加物がないと作れません。
添加物が心配なときに考えたいこと
添加物のすべてが危険というわけではなく、
その食べ物を作る上で欠かせないものもあることを知っておきましょう。
無添加のベビーフードとは
無添加のベビーフードというのは、各メーカーがいろいろな基準で書いているようです。
例えば、「保存料無添加」などです。
(2022年10月追記:優良誤認の可能性もあるので、
2024年あたりまでに「無添加」表記は見直されるでしょう*)
(参考資料…消費者庁食品表示基準Q&A_食品添加物の不使用表示に関するガイドライン)
保存料無添加のベビーフードがいいのか
基本的に、ベビーフードは瓶詰やレトルト、ドライ化させることで
保存料は必要がないように作られています。
保存料が必要なものは、長く日持ちがするもので、
なおかつ、高温加工などがされていないもののうちの一部
だと思っておくといいでしょう。
また、他には甘味料、着色料、香料なども無添加などと書かれていますが、
これらのものはベビーフードで使われることはほとんどありません。
必要がないからですね。
ベビーフードの賞味期限が長い理由
賞味期限が長いのは、密閉して高温高圧(レトルト)にしていたり、
水分量を減らす(ドライ)作り方であったりと、製造方法を工夫しているだけで、
添加物によって賞味期限を長くしているわけではありません。
有機(オーガニック)がいい?
赤ちゃんのみながらず、できる限り農薬は少ない方が安心です。
農薬がなるべく少ないものを赤ちゃんにあげたいというのは、
保護者共通の願いでしょう。
しかし、有機や無農薬で育てることができる野菜の種類は限られている
といわれており、すべての野菜をオーガニックで手に入れることは難しいでしょう。
また、虫などがついていたりするものを食べてしまっては大変ですので、
農薬にかかわらず、いずれにしてもよく洗う必要もあるでしょう。
離乳食で有機やオーガニック、無農薬と書いているものの注意
また、単品の野菜ペーストのようなものは、
野菜単品のため無農薬のみで作りやすいかと思いますが、
栄養バランスを考えて肉や魚、米などを加えるほど、
無農薬(オーガニック)という商品を作るのは困難になっていくでしょう。
気になるのであれば、値段が高めではありますが、
オーガニックのものを選んでみてもいいかもしれませんが、
その時には他の野菜や、肉や魚などのタンパク質も摂ることを忘れないようにしましょう。
「にんじんペースト」「ほうれんそうペースト」などは、
食材単体なのでオーガニックで作れるかもしれませんが、
複合的なものになると難しくなることも知っておくようにしましょう。
ただ、「絶対にオーガニックだけ」という選択にしてしまうと、
食品選択に偏りがうまれがちで、栄養の制限が出てしまう
オーガニックではないものも食べられる余裕を持てるといいですね。
有機とオーガニックと無農薬の違い
本来は「有機」と「オーガニック」は同じ意味なのですが、
日本においては、「オーガニック」「有機栽培」と書くためには
農林水産省の基準を満たさないといけません。
この基準では、有機栽培とは、化学肥料、化学的な農薬を使わず、遺伝子組み換えではなく、
2年以上経過した健康な土で栽培とされていて、農薬を使っていないという意味ではありません。

国で定められた基準(有機JAS規格)を満たさないといけないのですが、
そうでない商品が沢山あるのも事実です。
無農薬という表示は不当にあたることも
「無農薬」は、農水省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によると、
残留農薬がゼロであるような誤解を生じる、不当表示であるとして、
原則として認められていない表記といわれています。
海外と日本では基準が違うので、
海外の表記をそのまま使っている場合はオーガニックと名乗れたりするものもありますので、
この限りではありません。
残留農薬基準
残留農薬の基準も、食品衛生法に基づいて作られており、
ベビーフード協議会に加盟しているものについては、ビスフェノールAや放射性物質などの管理基準もあります。
オススメのベビーフードは?
レトルト?冷凍?有機?オーガニック?と種類が多いと悩んでしまいますが、
日本で売られているようなものであれば「笑顔になるほうで」と答えることもできます。
赤ちゃんの様子をみてみたり、いろいろなものにチャレンジしてみたりできるといいですね。
オーガニックのものは、野菜が単体ですが、いろいろな食材を食べる場合には困難です。
1つのものだけを続けるのではなく、いろいろな種類をとることによって、
なにかのとりすぎなどの栄養の偏りを防ぐリスクにもなりますので、
1つのメーカーや1つのブランドにこだわりすぎず、
いろいろ食べてみることがオススメです。
無添加や無農薬表記に踊らされないように
無農薬、有機栽培、オーガニックと書いてあると、つい飛びつきがちだと思います。
たしかに、農薬や添加物は少ない方が安心とはいえます。
しかし、本来添加物の必要ではないものに「無添加」と書いてあったりすることがあります。
例えば、赤ちゃん用のレトルト食品などに、「保存料、着色料 無添加」などと書いてあることがあります。
レトルトは高温高圧加熱しているので、本来保存料は必要ありませんが、
このような書き方をする商品もみられます。
「ベビーフードは色も付けないし、アタリマエだね。」と一歩引いてみられるような消費者になりましょう。
表示をみて、現在食べているものに対して不安になることもあるかもしれませんが、
表示だけに踊らされず、本当にそれが安心なのかを考えて、選ぶことも必要でしょう。
カインデスト商品パッケージに書いていない添加物(2022年10月追記)
theKindest(株式会社Mil)商品では、商品広告などには無添加としているものの、
実際は添加物を使っている事例があります。
これは、法に違反しているのではなく、
「栄養強化目的により添加物を加えた場合は表示しなくてもいい」という特例を使って、
栄養強化の添加物を使っているが食品表示などパッケージには一切記載していないというものです。
theKindest(カインデスト)では、
食品パッケージや広告に「添加物不使用」と書いているにもかかわらず、
実際はたくさんの添加物を使っており、
パッケージをみるだけでは、添加物が入っていることが全くわからないような商品が複数あります。
栄養添加は悪くなく、無添加としたことが問題
この記事でも紹介したように、添加物は決して悪いものではありません。
問題なのは、添加物を表記をしないことや、無添加と偽ることにあります。
消費者が「無添加だからいい」という思い込みをしてしまうと、
企業側がこのように「無添加」と偽って栄養添加食品を売るような世の中になってしまいます。

管理栄養士
ベビーフードは、育児する上でとても便利なものなので、上手に使いたいものです。
企業の事例を前向きにとらえ、消費者が賢くなっていきたいですね。
無添加だからと安易に飛びつくのはやめましょう。
消費者がより安心につかえるような、よい商品やサービスを期待したいですね
参考資料
株式会社MIL「【NEWS】当社商品における添加物表示に関するお知らせ(2020.11.11)」2022年10月14日閲覧
カインデスト「訂正シールについて(2021年1月29日更新)」2022年10月14日閲覧
著者執筆の記事一覧
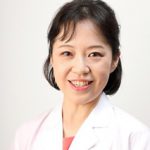
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
著者の記事
- 2024年7月16日コラム切り干し大根、栄養価が高いって本当?
- 2024年7月12日コラム離乳食冷凍小分けトレー(フリージング用容器)の使い方と注意点
- 2024年6月18日コラムしらすを離乳食に使う時、塩抜きしたほうがいい?いつまで?
- 2024年6月14日コラム保育園など児童福祉施設における食事の提供ガイド、改訂からみる現状の問題点と今後の課題点