離乳食のツナ缶:種類はノンオイル(水煮)?いつからOK?

ツナ缶 を 離乳食に使うことってありますよね。
よく、離乳食のレシピ本には、「ツナ缶(水煮)」等と書いてあったりします。
では、選ぶ際に、水煮とはどのものを指すのでしょうか。他のものではダメなのでしょうか。
また、ツナ缶はいつから食べられるのでしょうか。
今回は、ツナ缶選び方や開始時期についてどうしたらよいのかなどを管理栄養士が解説します。
注)正確には離乳期は、「離乳初期」といいますが、この記事では、読み手の方が親しみやすい、
「離乳食初期」と記載いたします。正式名称と異なりますがご了承ください。
離乳食にツナ缶を使う際の基本
ツナ缶を使用できる時期はいつから?
離乳食に、ツナ缶をとりいれるタイミングは、離乳初期でも中期でも構いません。

別に無理して離乳食初期に食べさせる必要はないです。
でも、初期ではダメということではないのですよ
別に無理して離乳食初期に食べさせる必要はないです。
でも、初期ではダメということではないのですよ

管理栄養士
ツナは離乳食の初期からでもOKですが、離乳中期からがオススメ。
赤ちゃんにツナを使うのは、離乳中期(生後7〜8か月頃)からがおすすめです。
しかしながら離乳初期であげてはいけないということではありません。
離乳食初期で食べられる理由
離乳食初期(5・6ヵ月頃~)の離乳食とは、滑らかなペースト状であることを意味します。
厚生労働省主導の研究班による「授乳・離乳の支援ガイド(2019年版)」によると、「白身魚から始める」と書いてあります1)ので、離乳中期から赤身魚と本に書いてあることが多いです。
しかしながら、これは離乳初期に使うことが禁止されていることではありません。白身魚のように身がやわらかいものからはじめて少しずつ赤身魚にするといいでしょう。
白身魚は、赤身魚に比べて、かゆみなどのもとになるヒスチジンを発生しにくいのも安心材料の1つではあります。
離乳食期の魚は、なるべく新鮮なものを選ぶようにと言われている理由の1つでもあります。
離乳食初期にツナ缶をあげるときの注意点
柔らかい食材であれば、離乳初期(5-6ヵ月頃)でも食べられます。
ツナを初期に避ける理由はなく、アレルギーなどの起きやすさは他の魚と大きな差はありません2)。
しかしながら、やわらかくなりやすい豆腐や白身魚などを先に食べてみることをオススメいたします。
まだペースト状にすれば、食べることはできます。
ただし、ごく稀ではありますが、ヒスタミン食中毒でかゆみがおきることもあります3)。

管理栄養士
白身魚にしても、ツナにしても、必要以上に怖がる必要はありません。
初めてあげる場合は、少量ずつ試しながら赤ちゃんの体調を観察しましょう。
ツナ缶の水銀、赤ちゃんは大丈夫?
マグロやカツオには、ごく微量ながら重金属(特にメチル水銀)が含まれる可能性があります。
妊娠中に水銀をとりすぎないように、気を付けていた人には、少し怖いかもしれませんが過度な心配は不要です。
胎児のときは、排出しきれず胎内に残る可能性があるため制限がありますが、生まれてからは気にする必要はありません2)。
日本において「すべての魚種等について、現段階では水銀による健康への悪影響が一般に懸念されるようなデータはない。」と発表されています。
ごく微量な水銀を気にしすぎるよりも、それらからとれる、栄養などの恵みを得ることが大切です。
そもそもツナ缶につかわれるものは、大型魚ではないので水銀はあまり多くありませんので、妊娠期にも問題なく使える食材です。
もちろん赤ちゃんにも安心して使うことができます。
ツナに含まれる栄養
ツナには赤ちゃんにあげたいさまざまな栄養が含まれます。
たんぱく質、鉄、不飽和脂肪酸(DHA,EPAなど)、赤身魚特有の栄養が入っています。
特に離乳食期に意識して摂りたい「鉄」をとりやすいのは、大きな魅力ですね。
しかし、離乳食で大切なのは、からだによいから・・・などといって同じものばかりを摂りすぎるのではなく、いろいろな食材をとりいれるということです。好みだけではなくその時の状況によって食べる/食べないがあるかと思いますが、いつでもムリなくトライしてみましょう。
【関連記事】離乳食の鉄補給:ツナ缶・ひじき・あさり缶は必要?
ツナ缶の魚の種類と名称
ツナ缶に使用される魚は、おもにカツオやマグロです5)6)。
どれもたんぱく質が豊富で、成長期の赤ちゃんにとって重要な栄養素を含んでいますので、選ぶときはどれでも構いません。
| 表示名 | おもな魚の種類5)6) |
| ライト(L) | キハダマグロ |
| ホワイト | ビンナガマグロ |
| マイルド | カツオ |

管理栄養士

ツナとシーチキンの違い
ツナは魚の総称で、かつおやまぐろを表します。シーチキンは、特定メーカーのツナ缶の商品名です。
シーチキンははごろもフーズ株式会社が所有する登録商標です。1958年に商標登録されました7)。

ツナ缶は油漬けが多いですが、赤ちゃんの離乳食に使うツナ缶は、「水煮」であるものが適しています。
ツナの水煮缶とは
水煮とは、油漬けではないものという意味です。
別の書き方として、
・ノンオイル(スーパーノンオイル)
・オイル不使用
などがあります。
いずれも同じ意味だと考えてもいいでしょう。
ただし、味付けが異なることがあります。
味付けの種類
ツナ缶の味付けの分類は難しいですが、大きく分けると、食塩無添加で味が薄いものと、味付けがしてありそのまま食べてもおいしいものとにわかれます。
- 食塩無添加
- 味付けあり(エキス・スープ・食塩など)
離乳食にオススメのツナ缶の種類と理由
離乳食にふさわしいツナ缶は、水煮(ノンオイル)であって、なおかつ食塩無添加のものです。
ツナ缶油漬けを離乳食に使う時に注意したいこと
では、油漬けや、味付けしてあるツナ缶はあげてはいけないのでしょうか?
それはそうではありません。ツナ缶油漬けを離乳食に使っても構いません。
水煮がオススメということであり、油漬けがダメというわけではありません。
ただし、油漬けは味付けが濃かったりすることもありますので、他の味付けをしないくらいでちょうどよいことが多いでしょう。
油漬けのツナを離乳食に使うときは、他の味付けをしないくらいでちょうどよいと覚えておきましょう。

私たちのレシピも多くはそのように記載します。これは他に味付けがある場合や、あくまでもオススメを書いているだけであって、もし手元にあるものが油漬のものしかなければ、他の味付けをいれないようにアレンジしていただいて構いません。
私たちのレシピも多くはそのように記載します。これは他に味付けがある場合や、あくまでもオススメを書いているだけであって、もし手元にあるものが油漬のものしかなければ、他の味付けをいれないようにアレンジしていただいて構いません。

管理栄養士
ツナ缶は加熱したほうがいい?
離乳食でツナ缶を使うときに、必ず加熱しなければいけないのでしょうか。
この答えは、NOです。
既にツナ缶は、缶詰として製造するときに十分な殺菌処理が行われています。
しかしながら、開封後に雑菌が付着する可能性はゼロではないので、開封後はすぐに食べるようにしましょうね。
加熱したほうがいい理由もあります。
例えば、味つけされているツナの場合は、水を加えて茹でこぼす(ゆで水を捨てる)ようにすることで、食塩を少し落とすことができます。
そのくらいであり、特に加熱の必要はありません。
衛生的に心配な場合は加熱してもいいですが、ツナ缶は加熱せずそのまま離乳食に使えますよ。
赤ちゃんがツナを嫌がる場合の対応
赤ちゃんにツナをあげたとき、赤ちゃんが嫌がることがあります。
理由はさまざまでわかりませんが、いずれにしても、無理にあげるのではなく、別の食材と組み合わせてみたり、調理方法を工夫してみるといいですね。
例えば、ツナのパサつきが気になるときは、おかゆに混ぜると、とろみがついて食べやすくなります。

管理栄養士
ツナ缶をつかったレシピリンク
ツナの利点は、缶詰のままなら常温で保存できるという点です。ちょっとタンパク質が足りないかな?とかなにかうま味が足せるかな?と感じたら手軽に魚が足せるのは嬉しいですよね。
そんなレシピをご紹介します。
また、ツナのかたまりが気になる場合は、
ブレンダーやすり鉢などで、なめらかにすりつぶすと食べやすくなることもあります。
一度嫌がった場合でも、数日から数週間経ってから再挑戦するとうまくいくこともあります。
離乳食や育児は、どうしても不安になってなにかと正解を求めてしまうものですが、「これがいい!」「こうしないとダメ!」みたいな正解がありません。難しいですが親子で無理なく楽しんでいろいろな食材を試してみてくださいね。ダメでも今回は「味見」の気分で、またいつか機会をみてあげてみましょう。
まとめ
離乳食でツナ缶を使う時には、水煮でなおかつ食塩不使用のものがおすすめです。
しかし、もし油漬けを使いたい場合は全くダメなわけではありません。味付けを少し薄くするために茹でこぼしてみたり、もしくは他に味付けをしないなどできるといいでしょう。
少しだけ油や塩分が落とせると安心ですね。離乳食には案外決まりはありません。食べてどうなのか、赤ちゃんが食べやすそうにしているかをみて、パサついているならおかゆにまぜてみるなど、食べられそうな方法をいろいろ模索してみましょう。
その過程が苦ではなく、楽しめますように。
注)正確には離乳期は、「離乳初期」といいますが、この記事では、読み手の方が親しみやすい、
「離乳食初期」と記載いたします。正式名称と異なりますがご了承ください。
参考文献
1)厚生労働省,「授乳・離乳の支援ガイド (2019年改訂版)」(閲覧日:2025年4月5日)
2)厚生労働科学研究事業「食物アレルギーの栄養食事指導の手引き2022」
3)日本経済新聞「はごろも、シーチキン672万個回収 アレルギー物質で」,2013年10月11日(閲覧日:2025年4月5日)
4)厚生労働省,通達「平成15年6月3日に公表した「水銀を含有する魚介類等の
摂食に関する注意事項」について(正しい理解のために),2003年6月(閲覧日:2025年4月15日)
5)はごろもフーズホームページ,商品情報(閲覧日:2025年4月11日)
6)いなば食品ホームページ,ツナ(閲覧日:2025年4月11日)
7)Jplatpat商標出願プラットホーム「第529904号:シーチキン」(閲覧日:2025年4月13日)
著者のプロフィール
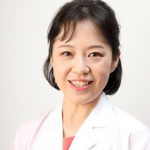
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
- 2025年4月18日コラム卵焼き器でレトルト食品を温めるのは要注意!理由と解説
- 2025年4月17日コラム離乳食のツナ缶:種類はノンオイル(水煮)?いつからOK?
- 2025年4月1日コラム賞味期限と消費期限の違いの解説と歴史的経緯
- 2025年3月29日コラム管理栄養士国家試験 合格率低下と平均年収からの考察
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。



