おせちの数の子やいくらは 赤ちゃんはいつから食べられる?
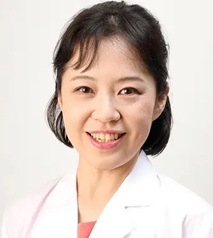
お正月の「おせち」には、様々な料理が入っていますが、子どもや赤ちゃんにあげていいものなのでしょうか。
地方や各家庭によって中身が違うとは思いますが、今回はおせちの定番の数の子や黒豆などについて考えてみましょう。
お正月。赤ちゃんと事故なく過ごすために
お正月に食べる「おせち」。
赤ちゃんにも食べられるかな?と心配になりますよね。
年末年始は病院もお休みのところが多いので、なるべく事故はさけたいものです。
よって、赤ちゃんの「初めての食材」は、
アレルギーなどの心配があるといけないので、年末年始は避けられるといいでしょう。
また、丸のみをしてしまう可能性のある
・黒豆
・ぎんなん
などには注意をして、
あげるときには、落ち着いて座って食べるように声掛けしたり、
見守ってあげるようにしましょう。

おせちのおもな食品と注意事項
全体的に、おせちは日持ちがするように、砂糖や塩を多めにつかって調理していたりするものが多いので、子どもにふさわしいとは言えないものが多いです。
おせちには、多少いろいろな地域性などもあるかもしれませんが、
今回は代表的なものを挙げて、赤ちゃんにあげるときの注意点などをお伝えします。
数の子(かずのこ)は何歳から? 赤ちゃんは食べてもいい?

かずのこは、魚卵です。
魚卵は幼児期に多いアレルギーです。
いくらと数の子は、同じ魚卵ですが、別のアレルゲンです。
しかし、数の子も注意する必要はあります。
薄切りや細かくしたら3歳頃から食べられるかもしれませんが、アレルギーがでる可能性もあります。
数の子は、魚卵アレルギーが心配ではありますが、いくらほどは多くはありません。
では、アレルギーが無ければ、どのくらいでも食べてもいいかと聞かれると、塩辛いことや硬いことも考えたいものです。
硬くてコロっとしているので切り方に注意したり、
塩蔵品で塩味が濃いことがあるので、少量のみにしておくといいでしょう。
伊達巻(だてまき)は赤ちゃんはいつから?
卵、魚のすり身などで作っています。卵アレルギーがなければ、9か月ごろから食べることはできます。
しかしながら、現在は卵の進め方を固ゆで卵のみですすめている可能性があるでしょう。
固ゆで卵と伊達巻を比べたら、加熱時間や温度の違いで伊達巻のほうがアレルギーは出やすいといえます。
市販品のものであれば、味も濃かったりしますので、縁起物として少しだけにしておくのがベターです。
卵とはんぺんで手作りする場合には、はんぺんや白身魚をすり身にして卵を加えていくかと思いますのでやはり卵アレルギーには注意しましょう。
いくら 、赤ちゃんはいつから食べられる?

魚卵はアレルギーの頻度が高めの食品で、幼児期にはじめて食べてアレルギーになるというケースのある食品です。
アレルギーの心配がある他、塩辛いので少量のみにしておきましょう。
また、生の塩蔵品であるため、衛生的なことも心配です。
からだがある程度大きくなった3歳頃からあげることはできますが、
はじめて食べる場合はアレルギーなどが出るかもしれないことを念頭において、
病院にいける時間帯などがいいでしょう。
このため、年末年始に初めて食べたりすることは避けておくといいでしょう。
*基本的には卵アレルギーや魚のアレルギーと魚卵アレルギーとの関係はありませんが、
念のためほかのアレルギーがある場合はさらに注意をしておくといいでしょう。
乳幼児期では初めてイクラを摂取して症状が誘発される場合がありますので、
アレルギーがなくても最初に食べるときには、少量のみにしてましょう。
黒豆は小さくきったりつぶして

甘くておいしい黒豆は、おうちでも煮たりするので、あげたくなってしまいます。
1歳すぎから食べることはできますが、面倒でも必ず小さく切ってあげるようにするか、
食べるときにしっかり見守り、飲み込みしないように気をつけましょう。
ぎんなん
ぎんなんは、刺激も強いので、赤ちゃんにはあげないようにしましょう。
海老は赤ちゃんには硬い他、アレルギーの心配も
アレルギーの心配もありますので、初めて年末年始などにあげることは避けておくといいでしょう。
また、それだけではなく、海老は、硬さも心配です。
指でつぶすことができず、弾力があるので、
ある程度しっかり噛めるような年齢になってから、様子をみながらあげるといいでしょう。
お正月より前に食べさせておくと安心です。はじめてならお正月の時期にあげないようにしましょう。
かまぼこは弾力があり、塩分も高め

かまぼこは、塩分が多く、弾力があるので普段は控えた方がベターですが、
少量であれば1歳から
であればOKです。
ただし、弾力と塩分が問題なので、薄くきって味付けのように少量使うなど、あまり多くないほうがいいでしょう。
かまぼこやカニかまぼこの多くは、複数の魚からできていますが、あわせて卵白を使っていることが多いです。
また、はんぺんにも卵白を使っていることが多いでしょう。
詳しくは表示をしっかりみて確認し、卵アレルギーが心配な方は避けておくといいでしょう。
栗きんとん
栗は、ナッツ類に入るのでアレルギーが心配されがちですが、ナッツ類の中では、そこまで症例数は多くありません。
とはいえ、栗は丸くて硬いことがあります。
丸のみしないように、よく噛むことがわかる年齢からあげるようにしましょう。
あくまでも目安ですが年末年始は気を付けて
各食材別に書きましたが、あくまで目安です。
ご自身のお子さんの発育状態やその食材の様子なども異なりますので、
必ず保護者様ご自身で見てご判断をお願いします。
年末年始はいろいろ忙しく、注意をそらしがち、お餅を飲み込んでしまったりすることのないように、
食事時間は、しっかり落ち着いて過ごしたいものです。
アレルギーの可能性がありそうなものは、はじめてあげるの時が年末年始にならないようにしておくと、安心ですね。
何かあったときに病院に気楽にいけるときにはじめておくのが、「はじめて食材」をあげるときのポイントです。
参考資料
[*1]総務庁,教育・保育施設等における事故防止及び 事故発生時の対応のガイドライン
著者のプロフィール

-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!
コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証
コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性
コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。







