離乳食のうどんはいつから食べられる? 月齢と目安量
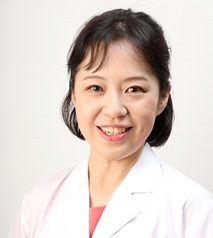
赤ちゃんは、ちゅるちゅると吸って食べることが出来る麺類が好きだったりしますね。
うどんは何ヶ月からどのくらい食べられるのでしょうか?

離乳食のうどんは6ヶ月か7ヶ月頃~
実際のところ、離乳食にうどんをあげるのは生後7ヶ月頃がよいでしょう。
ただ、これにはいろいろな理由があります。
離乳初期(5·6ヶ月頃)は、うどんをあげてはいけないの?
離乳初期というのは、舌で後ろに食べ物を送ってゴックンと飲めるくらいの咀嚼の状態です。
だいたい離乳食をはじめて1-2カ月の生後5ヶ月~6ヶ月頃だと
このくらいの口腔発達のことが多いでしょう。
小麦アレルギーの可能性はあるかもしれませんので、
もしどうしても小麦アレルギーが気になるという場合は、小麦を少し含むベビーフードを試してみたり、
野菜ペーストに水溶きの小麦粉を少しだけ使ってからでもいいかもしれません。


管理栄養士
うどんをつぶさず食べられるのは7ヶ月頃
離乳食を食べて少し経つと、舌でペタッとつぶして食べるということができるようになったり、
ある程度の大きさのもののならそのまま飲み込んでしまうことができるようになります。
このことから、赤ちゃん用として販売されている麺であれば
7ヶ月頃から食べられることが多いかと思います。
離乳食アドバイザー講座(▶)で咀嚼機能にあわせた調理基準についてご説明しています
赤ちゃん用のうどんなら7ヶ月としている理由
・薄い
・短い
・塩分が少ない
赤ちゃん用のうどんは、塩分を含まないということがポイントとされています。
しかし、それだけではなく、
実はとても薄いことも特徴の1つです。
うどんは、ほとんどそのまま飲み込んでしまうことも多いかと思います。
しかし、薄い場合は窒息事故が起きにくいので丸呑みしても安心といえます。

離乳食のうどん 月齢別調理法
離乳食を最初に食べる頃はまだぺたーとしたヨーグルト状が食べやすく消化もしやすいのでおすすめです。

うどんをその頃にあげたいということであれば、つぶしがゆのように、「つぶしうどん」にする必要があります。
しかしながらうどんをつぶすのはけっこう手間ですので、離乳食でのうどんは7ヶ月頃でもいいいのではないでしょうか。
そのあと、豆腐くらいの硬さのものが食べられるようになったころでも、硬くて長いうどんは喉に詰まってしまうといけないので、ハサミなどで短くきってあげるといいでしょう
離乳食のうどん 月齢別目安量
離乳食のうどんの量は、6ヶ月頃は10g程度から成長に伴って1歳頃には100gに近づいていきます。
しかしながら、この量は厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」には書いてありません。なぜ書いていないのかということにも回答はあります。それはそこまで量を追い求めず、赤ちゃんの食欲にあわせてよい からです。
離乳食の量は赤ちゃんの食欲や運動量、他に食べる食材などによっても変わるものですので、あまり追い求めないようにしましょう。
下記、月齢ごとにご紹介します。
本来は「離乳食初期」などの呼び方はなく、「離乳初期」が厚生労働省の定める正式名称になります1)が、俗に離乳食初期といわれるのでここではそのように書きます。ご了承ください
6ヶ月頃(離乳食初期)のうどんの量 10g~
離乳食を始めるころは、少しからはじめるといいでしょう。
もし、今まで小麦粉を含むものを食べていないということであれば、
少量で様子をみるといいでしょう。
この「少量」に特段目安量があるものではありません。
たとえば保護者がうどんを食べるときに、
少しだけスプーンの裏などでぎゅっとつぶしてペーストにしてあげてみる程度がいいでしょう。
それ以上食べられるようであれば量を増やしていっても構いません。
7ヶ月~8ヶ月頃(離乳食中期)のうどんの量 30~50g
離乳食をはじめて1-2カ月経つと、赤ちゃんも食べることに慣れてきますね。だいたいうどんなら30~50gくらいが食べられるかもしれません。
これはエネルギーや糖質の量で比べると、全がゆ50~80gに該当することになります。
ただ全がゆは水分量によっても大きく異なりますし、
うどんだと飲むように食べてしまうこともあるので、この限りではないかもしれません。
あくまでも野菜や肉魚などの「おかず」もうどんと同量かそれ以上くらいを食べているかをチェックしましょう。
9ヶ月~11ヶ月頃(離乳食後期)のうどんの量 60~80g
この頃だからうどんがこのgになるというわけではありませんが、
生後9ヶ月頃から母乳(またはミルク)と食事のバランスが、
だいたい半々か少しずつ食事からエネルギー(カロリー)を摂っていく頃になりますので、
うどんは60-80gくらいを目安量としておくといいでしょう。
あまりうどんを多く食べ過ぎて母乳やミルクを飲まなくなった。。。ということがないようにしたいのがこの時期です。
離乳食後期は本来は「離乳後期」と呼びますが、この頃だからこの量というわけではなく、
これは咀嚼のバロメーターを示すので、離乳後期は歯ぐきでかみつぶせる頃だと理解しましょう。
12ヶ月~1才半頃(離乳食完了期)のうどんの量 90~120g
離乳食完了期とは言わず、本来は「離乳完了期」と言う時期です。
なぜ離乳完了期というと、エネルギーの多くを食事から摂れるようになる時期だからです。
母乳(またはミルク)をやめるということではなく、
この頃から栄養の多くを食事から摂れるようになるということなので、量などを追い求めず
、下記のことに気を付けましょう。
・元気でいるか
・食欲があるか
・他の肉魚などのたんぱく源や野菜類などのおかずを食べているか
赤ちゃんにうどんをあげるときに注意したいこと
実際に離乳食の時にうどんをあげるときにはどのようなことに注意をしたらいいでしょうか。
注意は「アレルギー」「バランス」「塩分」「咀嚼」の4つです。
うどんで気になる小麦アレルギー
乳児に多いアレルギーは、圧倒的に「鶏卵」でその次に「乳」「小麦」と続きます。
小麦は乳児でもアレルギーが起こりうる食品ではありますので、
初めて食べるときは少しだけにしておくと安心です。
この「安心」というのは、アレルギーを起こさないことを意味しているわけでも、
アレルギーの予防のために少しずつ増やしていくほうがいいという意味でもありません。
最初にたくさん食べてしまって症状が強くでるよりも、
少しにしておいたほうがいいということになります。
このほかにもはじめてあげるときは病院のあいている時間にあげるということもポイントになります
もしどうしても小麦アレルギーが気になるという場合は、
小麦を少し含むベビーフードを試してみたり、
野菜ペーストに水溶きの小麦粉を少しだけ使ってからでもいいかもしれません。
しょうゆや味噌などにも「大豆」や「小麦」が原料として含まれていますが、
反応しなくても小麦製品や大豆製品ではアレルギーを起こすことがありますので
ごくごく微量で大丈夫だから多くても大丈夫という保証はありません。
あくまでもバランスよく
うどんの量が気になるものです。 はじめての育児は心配だったり、どれが正解なのかと追い求めたくなったりしますよね。
しかしながら赤ちゃんの運動量、母乳やミルクの哺乳量はさまざまです。
また、上記に記したうどんの量は、
肉魚などのたんぱく源と野菜をしっかり食べているうえでの炭水化物量になります。
よって、
いちばん調整が効く食べ物だと思ってもいいでしょう。
目安の量を追い求めずにお願いします。
「うどんはお腹の好き具合にあわせて量が異なる」と考えるといいですね。
塩分のとりすぎに注意
うどんは塩分を含むから「塩分なしがいい」のでしょうか。
たしかに乳児は腎臓の発達が未熟のため多量の塩分を処理することができません。しかしながら、塩分を意識するときは単体より全体に目を向けてみましょう。
例えばうどんの場合は下記の2つの塩分があります。
- うどんの中に練りこまれている塩分
- うどんの外のスープや味付けの塩分
「うどんが塩分なしだから」
「スープが薄味だから」
と、スープもたくさん飲み干してしまったら
トータルとして塩分をたくさん摂ることにつながってしまうかもしれません。
反対にうどんの中に多少塩分が含まれていれば、
味を付けずに単体でもおいしく食べるかもしれません。
この極端な2例を比べるとどちらが塩分が多いのかはわかりません。
大切なのは、塩分は料理全体で考えて「大人の半分くらいの味付けだな」と感じる程度ということです。
あいまいな基準ではありますが、1つ1つの塩分量を気にするよりもこれが実践的でしょう。

そうですよね。
塩分が気になりますので、
・次の食事は薄味にしてみる
・コップなどにお水やお湯をもらって一旦うどんを漬けて少し味を落としてからあげる
などはどうでしょう?
そうですよね。
塩分が気になりますので、
・次の食事は薄味にしてみる
・コップなどにお水やお湯をもらって一旦うどんを漬けて少し味を落としてからあげる
などはどうでしょう?

管理栄養士
うどんを噛まないご相談:咀嚼しにくい うどん
うどんは実は硬いことが多いのです。
離乳後期(歯ぐきでつぶせる時期)は、やわらかいハンバーグや、バナナの5㎜スライス程度のものを食べることができますが、この目安は大人の親指と人差し指でつぶせる程度になります。
うどんを大人の指でつぶしてみましょう。

讃岐うどんは、近年では冷凍うどんの定番ですが、時折、加工でんぷんとしてタピオカでんぷんが含まれていることがあります。
これは大人にとってはうどんのコシを感じてとても美味しいものです。
しかし、赤ちゃんにとっては噛みにくいものになります。
大人の指ではつぶしきれない硬さの時には丸呑みしやすくなってしまうかもしれません。
しっかりやわらかく茹でるか、別の種類のうどんを選ぶといいかもしれませんね
咀嚼しやすいレシピをご紹介します
手づかみできる うどんレシピ
うどんは硬さによってはそのまま飲みやすい食材です。
しっかり噛んでもらうためにはおやき風にするのもおすすめです。
【離乳後期、完了期】手づかみ焼きうどん
材料)
茹でうどん …1袋
野菜 …合計 30g
鮭 …30g
かつお節 、小麦粉 、かたくり粉
を使います。この1品で野菜も魚も摂れますので栄養バランスの大きな偏りも防げそうですね
もしよければお試しください

よくあるご質問
うどんばかり という日もありますよね!
私もありますよ!
そういう時は次に気づいたときにおかずを多めに食べるようにすれば全然OKです。
うどんだから何gというのではなく、うどん茶碗1杯くらいなら、
同じくらいの量のおかずをどこかで食べさせたいなぁと思っておいてくださいね。
少しずつおかずを多めにとる習慣があれば、「うどんだけの日」があっても大丈夫そうですよね。
2-3日のうちにどこかで食べられたり、副菜として考えられるといいでしょう。
参考文献
- 厚生労働省.「授乳・離乳の支援ガイド」 (URL)(2025年7月6日 閲覧)
著者のプロフィール
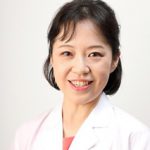
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事




お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。







