栄養士と管理栄養士の違い。社会人でもとれる資格は?
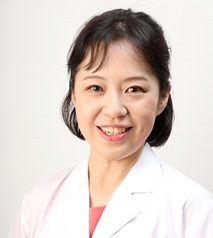
栄養士と管理栄養士は何が違うのか、社会人でも取得したいときにはどうしたらいいのかを解説いたします。
また当協会などが認定している民間資格はどう違うのかにも触れます。
栄養士とは
栄養士とはどのような資格なのでしょうか。
簡単にいうのなら、
栄養士は、「栄養士」として健康な人への栄養指導や給食運営ができる国家資格です。
都道府県知事交付び国家資格
栄養士に関することは栄養士法で決まっています。
その栄養士法には、栄養士について下記のように記されています。
第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)施行日:令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)
つまり、
栄養士とは、都道府県知事から免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導にあたることができる国家資格です。
おもに健康な方を対象にして栄養指導や給食の運営などをすることができます。
栄養士の資格がない人が、栄養士と称して栄養指導にあたることは法律で禁止されています。
通信教育(通信講座)では栄養士は取得できない
栄養士になるには、必ず栄養士養成校に入学しなければなりません。
養成校は、厚生労働大臣の認可された施設である必要ががありますので、
栄養士になりたい場合は認可されている学校であるかをよく確認しましょう。
栄養士は、通信教育では取得することはできません。
社会人でも栄養士になれる?
社会人でも栄養士になることができます。
専門学校や短期大学などで2年間以上通って必要な単位を取得できれば、栄養士になることはできます。
社会人のための入学試験を設けているところもありますので、調べてみてもいいでしょう。
夜間通学で栄養士になれる?
編入や夜学はありません。
栄養士になるには、専門の過程を、昼間に2年以上は通う必要がありますので、
社会人を続けながらはなかなか難しいとは思いますが、
夜働くなどであればできないことではないかもしれません
管理栄養士とは
簡単にいうのなら、栄養士の上位資格です。
管理栄養士は、栄養士免許をもっている必要があり、
なおかつ国家試験に合格することで、
「管理栄養士」として傷病者への栄養指導や高度な専門知識をもった
各状況に応じた給食管理や指導ができる国家資格です。
厚生労働大臣交付の国家資格
管理栄養士に関することも、栄養士法によって決まっています。
栄養士法には、管理栄養士について下記のように記されています。
第一条 ② この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)施行日:令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)
つまり、
管理栄養士とは、厚生労働大臣から免許を受けて、病気など方に栄養指導したり、
より高度な栄養指導や細かい特別な配慮が必要な方の給食管理や食事指導をおこなうことができます。
管理栄養士の資格がない人が栄養士と称して栄養指導にあたることは
法律で禁止されています。
管理栄養士設置義務の施設
また、施設では管理栄養士の設置義務があることがあります。
健康増進法では、下記のように定められています。
(特定給食施設における栄養管理)
健康増進法(平成十四年法律第百三号)施行日:令和四年六月二十二日(令和四年法律第七十七号による改正)
第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
保健所が調査を行って基準に合致するとされた特定給食施設には、管理栄養士の必置指定が通知されます。
管理栄養士は通信教育でとれる?
管理栄養士は、通信教育(通信講座)などで取得することはできません。
ユーキャンの管理栄養士通信講座は栄養士向け
一時期、通信講座のユーキャンで、管理栄養士国家試験対策講座がありました(2022年現在、この講座はありません)。
今もいくつかの管理栄養士の国家試験対策講座などが通信講座などであります。
しかし、管理栄養士の通信講座は、
栄養士の資格があり、なおかつ管理栄養士の国家試験受験資格(実務経験1-3年)がある人向けの講座であって、
栄養士以外の方が通信講座でとれるものではありません。
通信講座のユーキャンでは、栄養士の資格がない人は管理栄養士の資格はとれませんが、
栄養士資格がある人は、下記のユーキャンが出している国家試験対策の本がよさそうです。
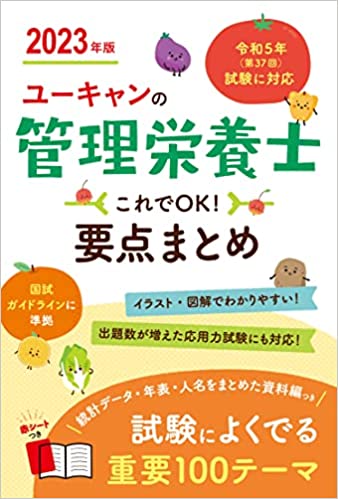
管理栄養士になるには
管理栄養士になるには2通りあります。
①栄養士養成校で必要単位を取得して卒業し、栄養士になってから実務経験*を積んでから管理栄養士国家試験を受験(最短で5年)
②管理栄養士養成校で必要単位を取得して卒業し、管理栄養士国家試験を受験(最短で4年)
*実務経験:栄養士養成校の修業2年過程の場合は実務経験3年以上などになります。 詳しくは>>栄養士法
管理栄養士になるには、まず学校に通って栄養士になる必要があるのと、最終的には必ず国家試験に合格する必要があります。
卒業しただけで、管理栄養士になれるような近道は存在しませんし、栄養士ではない人が国家試験を受験することもできません。
栄養士養成校、管理栄養士養成校は、厚生労働大臣の認可された施設である必要があります。
管理栄養士を目指したい場合は、入学前にしっかり確認しましょう。 >>全国栄養士養成施設一覧
管理栄養士は医師、他医療従事者との連携が必要
管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導をおこなう際には、主治医の指導を受けなければなりません。
病気などの方に医師の指導なく栄養指導することは、管理栄養士であってもできません。
ただし、場合によっては医師の指示に疑問が生まれたり、
もっといろいろな背景を聞きたくなることがあります。
傷病者に対しての栄養を考えるには、医師や看護師などその他従事者の人と一緒に話し合うことがとても大切です。
これをNSTといいいます。
NST専門療法士
NSTとは、栄養サポートチーム( Nutrition Support Team)の略で、傷病者にとって最適な栄養療法を多職種で考える医療チームのことです。
特に静脈栄養や経腸栄養が必要な場合が多いですが、普通にごはんが経口で食べられる場合でも、話し合う機会があるといいシーンもたくさんあります。
NSTの構成メンバーは、医師や管理栄養士だけでなく、看護師、薬剤師、臨床検査技師、歯科医などが入ることが多いですが、もっと多くの職種の人が入ると良いとも言われています。
日本臨床栄養学会による「NST専門療法士」という民間資格もあります。>>日本臨床栄養学会「NST専門療法士」
NSTに参加することはこの資格がなくても管理栄養士であれば可能ですが、あるとより高度な指導ができるような知識が得られそうですね。
また、管理栄養士ではなくてもNST専門療法士を受講することができ、栄養の知識を学べそうです。
栄養士の方におすすめしたいプラスの資格
栄養士であれば、離乳食の指導をすることができます。
母子栄養協会の離乳食アドバイザー、幼児食アドバイザー、
妊産婦食アドバイザー、学童食アドバイザー、母子栄養指導士は、
いずれも民間資格ですが、栄養士養成校の授業より詳細な知識が得られます。
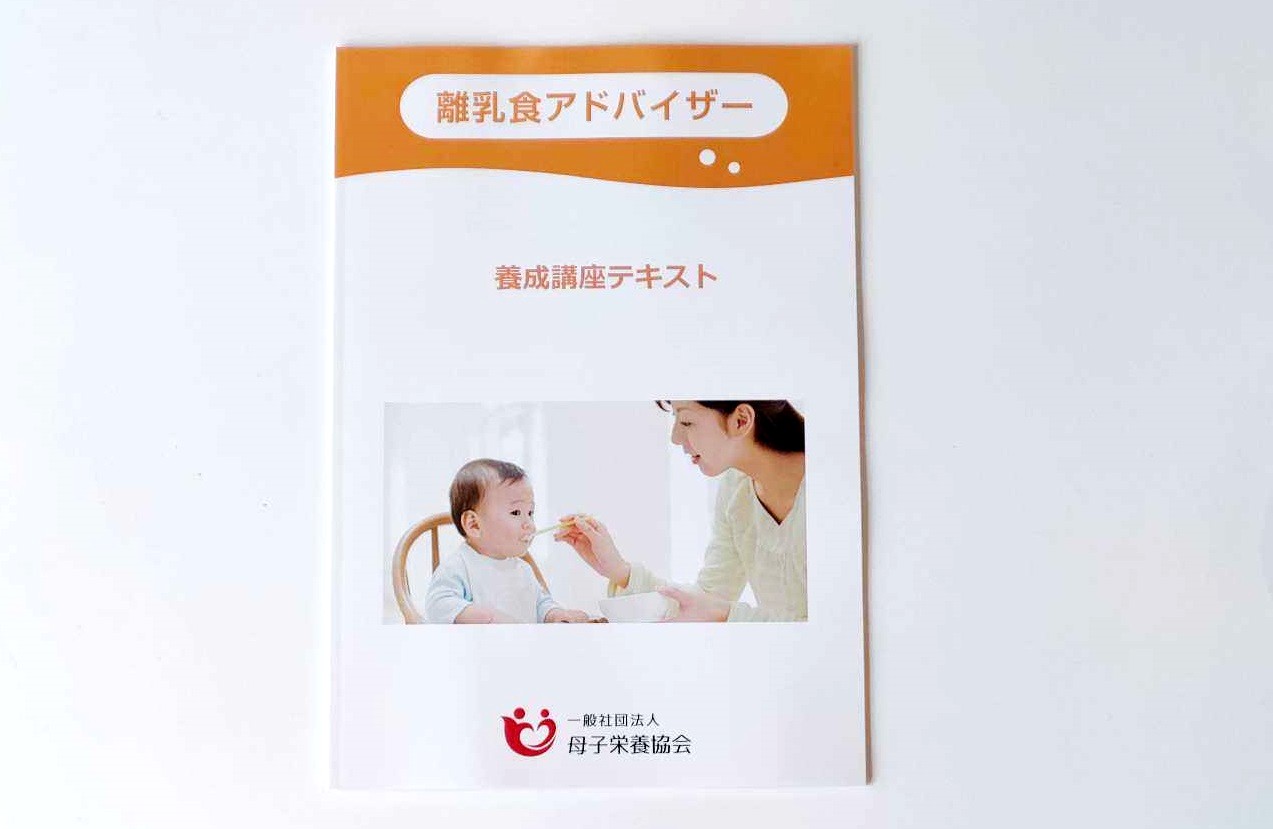
離乳食アドバイザー等になると何が学べる?
保育園などに勤めたり、保健所などで乳幼児検診の食事相談で困ったり、
自分の答えに疑問をもったことはありませんか?
また、自身や身内にお子さんが生まれたのをきっかけに
「離乳食ってどうやってやるんだろう?」と
レシピ本を買って勉強しようと思ったことはありませんか?
そのような疑問がある場合は、アドバイザー講座をおすすめいたします。
母子栄養協会の代表は、乳幼児の栄養相談経験多数であり、
さまざまな学会発表や商品開発、本の執筆をしている管理栄養士です。
テキストは、各種ガイドラインを複合的に組み合わせたうえで
その元となっている考え方や論文をわかりやすく解説しています。
いわゆる普通の本にあるような知識ではなく、その情報の根拠を学ぶことになります。
栄養士養成校で離乳食や幼児食の授業がごくわずか
母子にかかわる栄養学(離乳食や幼児食など)に関する授業は、
栄養士養成校ではほんの数時間で終わってしまいます。
栄養士が子どもに関する食事を学ぶ時間は、
幼児食と離乳食作成1コマずつ程度で終了であることがほとんどではないでしょうか。
実際に保育園に勤務してもわからないことがたくさんあり、
ネットで調べてしまったり、
通信講座などで学んでしまったりすることもあるかもしれません。
それらは本当に正しいでしょうか。
また新しいガイドラインを独自に読みこんでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、
そのガイドラインの読み方はあっていますでしょうか?
食事を用意するということの保護者の負担や、
食情報にあふれて不安に思う保護者の気持ちなども学び取っていただけますと幸いです。
疾病がある場合の食事指導内容は含みません
傷病者の指導は、医師の指導を聞き、管理栄養士がする必要があるため、
当協会のアドバイザー講座には、疾病がある場合のケアは内容に含んでいません。
アレルギーの知識などは内容に含まれますが、ホームケアのみとなっています。
また、アレルギーについては医師の診断がどのようにくだるのかの説明などにとどまります。
妊産婦食アドバイザーなどで「妊娠糖尿病」や「妊娠高血圧症候群」については
発症機序や食事との関係などについては学びますが、実際の指導については、あえて内容に含みません。
医師の診断なくして食事指導ができないためでもありますが、発症機序がわかれば管理栄養士なら理解はできるように設計しています。
管理栄養士であってアドバイザー資格がある場合は、
会員専用LINEにてどのようなことを注目して栄養指導をしていったらいいかを実際の例を差支えのない範囲でうかがいながら講師が直接回答いたします。
栄養士ではなくても離乳食アドバイザーになれます
栄養士ではなくても、母子栄養協会の離乳食アドバイザー、幼児食アドバイザー、妊産婦食アドバイザー、学童食アドバイザーを取得することはできますが、試験に合格していただく必要はあります。
試験はわからないことがありましたら、何度でも相談可能ですし、
不合格でも何度でも再試験は無料でできます。
ただ、お子さんを育てるというだけの場合は、アドバイザー講座ではなく、
アドバイザーさんが開催する離乳食教室などをまずは受講してみたり、相談してみることをおすすめします。
当協会のアドバイザー資格は、決して難しいわけではありませんので
栄養の知識がなくても大丈夫です。
しかしながら、ある程度の金額がかかるため、
資格を取得する必要があるかはよくお考えになられてからご受講ください。
例えば、
・離乳食の本当の意味が知りたい
・妊娠中に食べていいもの悪いものの理由が知りたい
・食事や栄養に対しての不安がある
・保育士や看護師、医師、歯科医師などで食事や栄養の知識を得たい
という方にはおすすめさせていただきます。
離乳食・幼児食アドバイザーで保育園の調理ができる?
離乳食アドバイザーや幼児食アドバイザーで保育園の調理ができるか?というご質問を受けることがあります。
結果から申し上げると、可能です。
保育所(保育園)では、栄養士の設置義務がありませんので、誰でも調理することができます。
第三十三条 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)施行日: 令和四年四月一日
*児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める
この法律でいうところの「調理員」は調理師を意味するものではないので、誰でも構わないということになります。
離乳食アドバイザーや幼児食アドバイザーがあってもなくても、保育園で調理をすることはできます。
しかしながら、さまざまなガイドラインを知り、どのような硬さに調理をすると事故が少なくなるのか、子どもの食べる環境はどのように整えるべきなのか、衛生なども含めて考えなくてはいけませんので、その知識はアドバイザー講座などを受講しておくことをおすすめいたします。
また、衛生に関することは、
施設長を交えてしっかりと管轄保健所の指導を受けておきましょう。
-


栄養士は都道府県知事による免許で、管理栄養士は国家試験に合格する必要があります。業務の幅や責任も異なります。管理栄養士は疾病を持つ人を医師の診断のもと、栄養指導できます。
-


栄養士養成課程のある専門学校や大学を卒業すると、都道府県発行の免許を取得できます。
-


夜学や通信教育はありませんのて、働きながらは困難です。4年制の管理栄養士養成課程を卒業して国家試験を受けるか、2年ほど学んで栄養士になってから、栄養士として一定の実務経験を積んだ上で試験に挑む方法があります。
まとめ
栄養士や管理栄養士は、栄養に関する国家資格です。
病気などの方に栄養指導ができるのは管理栄養士になります。
母子栄養協会の各種アドバイザー資格は、さらに母子の分野の学習を補うために使うことをおすすめします。
また、栄養士ではなくても母子栄養協会のアドバイザー講座を受講することができます。
栄養の知識を得ることで、巷にあふれる間違えた栄養情報などに惑わされなくなることはとても大切です。
ご興味があれば、母子栄養協会の各種アドバイザーのご受講を検討してみてください。
参考文献
- 総務省. 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号). 令和四年法律第六十八号. 2022年6月;: (URL)(2025年7月6日 閲覧)
- 日本臨床栄養学会.NST専門療法士 (URL)(2025年7月6日 閲覧)
- 内閣府.児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) (URL)(2025年7月6日 閲覧)
著者のプロフィール
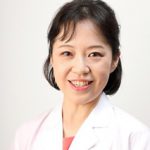
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事




お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。









