食中毒の潜伏期間と症状を徹底解説|食品別の特徴と対策
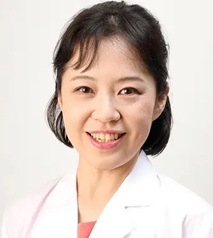
食中毒は年間を通して発生する健康被害であり、原因となる病原体や摂取した食品によって潜伏期間や症状が大きく異なります。この記事では、食品の種類ごとに発生しやすい食中毒の潜伏期間と症状・予防について詳しく解説します。
食中毒とは
食中毒とは、有害な微生物(細菌やウイルスなど)や化学物質、自然毒などが含まれた飲食物を摂取することによって起こる健康障害のことです。厚生労働省のデータによると、2024年の食中毒発生件数は1,000件以上に上り、その原因は多岐にわたります1)。
食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つの原則が重要です2)。
食中毒の症状は原因物質によって異なりますが、主な症状には下痢、腹痛、嘔吐、発熱などがあります。特に注意すべきは潜伏期間の違いで、数時間で発症するものから数日、さらには数週間後に症状が現れるものまであります。
おもに肉に関連する食中毒
肉類は細菌による汚染が起こりやすく、特に生肉や加熱不十分な肉料理は食中毒のリスクが高まります。
食中毒の潜伏期間と症状一覧表(肉類)
| 病原体 | 潜伏期間 | 主な症状 | 原因食品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サルモネラ3) | 6~48時間 | おう吐、腹痛、下痢、発熱 | 加熱不足の卵・肉・魚料理、生卵、オムレツ、自家製マヨネーズなど | 乳幼児や高齢者は症状が重くなることがある |
| カンピロバクター4) | 1~7日 | 下痢、発熱、おう吐、腹痛、筋肉痛、血便が混じることもある | 生や加熱不足の肉(特に鶏肉や鶏レバー) | 感染数週間後にギラン・バレー症候群を起こすことがある |
| 腸管出血性大腸菌(O157、O111など)5) | 3~8日 | 激しい腹痛、下痢、下血 | 加熱不足の肉、生野菜・井戸水など | 重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)など命に関わる合併症の恐れあり |
肉類の食中毒予防方法
肉類による食中毒を予防するには、中心部まで十分に加熱すること、調理器具の使い分けや手洗いの徹底が必要です。
特に生の肉を扱った後は必ず手洗いをし、包丁やまな板は生野菜などの加熱しない食品を先に切り、生の肉は後で切るようにしましょう 2)。

【関連記事】O-157とは?知っておきたい感染のリスクと予防策
おもに魚介類に関連する食中毒
魚介類は鮮度が良くても食中毒を引き起こす病原体が存在する場合があります。
特に夏場は注意が必要です。
食中毒の潜伏期間と症状一覧表(魚介類)
| 病原体 | 潜伏期間 | 主な症状 | 原因食品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 腸炎ビブリオ6) | 4~96時間 | 激しい下痢、腹痛、血便が混じることもある | 魚介類の刺身や寿司など | 夏に発生が多い、高齢者は症状が重くなることがある |
| アニサキス7) | 数時間~10数時間 | みぞおちの激しい腹痛、吐き気、嘔吐 | サバ、サンマ、アジ、イワシ、ヒラメ、サケ、カツオ、イカ等の海産魚介類の刺身 | 食中毒発生件数第1位、-20℃で24時間以上の冷凍で予防可能 |
| ノロウイルス8) | 1~2日 | おう吐、激しい下痢、腹痛 | ウイルスを含む二枚貝(カキ等)を生や加熱不足で食べた場合 | 感染力が強く、冬季に多発、中心部85~90℃で90秒間以上の加熱で予防 |
魚介類の食中毒予防方法
魚介類の食中毒を予防するには、魚介類は流水でしっかり洗い、生魚を食べる前に新鮮さを確認することが重要です。アニサキスが心配な場合は-20℃で24時間以上冷凍処理をするか、中心温度60℃で1分以上の加熱を行うことが効果的です7)。
おもに野菜・果物に関連する食中毒
野菜や果物を原因とする食中毒は多くはありませんが、生で食べる場合などは特に注意が必要です。
食中毒の潜伏期間と症状一覧表(野菜・果物)
| 病原体 | 潜伏期間 | 主な症状 | 原因食品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 腸管出血性大腸菌(O157、O111など)5) | 3~8日 | 激しい腹痛、下痢、下血 | 生野菜・生肉・井戸水など | 農業用水や家畜の糞便からの汚染が原因 |
野菜・果物類の食中毒予防方法
野菜や果物の食中毒を予防するには、生野菜はよく洗ってから食べることが基本です5)。
また、生の肉に使った包丁で生野菜を切らないよう、調理器具の使い分けも重要です5)。

食品全般に関連する食中毒
調理方法や保存状態によって、様々な食品で発生する可能性がある食中毒もあります。
食中毒の潜伏期間と症状一覧表(食品全般)
| 病原体 | 潜伏期間 | 主な症状 | 原因食品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌9) | 1~6時間 | 吐き気、おう吐、腹痛 | おにぎり、いなりずし、巻きずし、弁当、調理パンなど | ヒトの皮膚、鼻や口の中、傷口に常在、下痢はあるが発熱はしない |
| ウェルシュ菌10) | 6~18時間 (平均10時間) | 腹痛、下痢 | 煮物、カレー、シチューなどの煮込み料理 | 芽胞を作るため通常の加熱調理では死滅しない |
野菜・果物類の食中毒予防方法
食品全般の食中毒を予防するには、調理前の手洗い、適切な温度管理、調理後の食品を常温で長時間放置しないことが重要です。
特にウェルシュ菌による食中毒を防ぐには、煮込み料理は常温のまま放置せず、できるだけその日のうちに食べきり、保存する際は小分けして早く冷ますことが大切です10)。
【関連記事】保育所におけるヒスタミン中毒「かつおだし」から学ぶ
その他の食中毒(自然毒)
食中毒には、いわゆる菌によるものの他、天然毒素ともいわれる自然毒によるものがあります。
食中毒の潜伏期間と症状の一例(自然毒)
| 分類 | 原因物質 | 潜伏期間 | 主な症状 | 原因食品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然毒(植物性) | ジャガイモの芽(ソラニン) | 数時間~24時間 | 吐き気、嘔吐、腹痛、頭痛 | 発芽したジャガイモ、緑化したジャガイモ | 加熱しても毒性は失われない |
| 自然毒(植物性) | 毒キノコ | 30分~数日 | 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、幻覚、肝臓障害 | 毒キノコ(ドクツルタケなど) | 種類によって症状や潜伏期間が異なる |
天然毒による食中毒を予防するには、素人判断で野生のキノコを採取して食べない、ジャガイモの芽や緑色になった部分は完全に取り除くなどの注意が必要です2)。
食中毒予防のポイント
農林水産省が推奨する食中毒予防の3原則は以下の通りです2)):
つけない
- 生の卵・肉・魚介類にさわったら、よく手を洗う
- 包丁やまな板は生野菜などの加熱しない食品を先に切り、生の肉や魚介類は後で切る
- 肉や魚介類などの汁が、生で食べるものや調理済みの食品にかからないようにする
増やさない
- 肉や魚介類を冷蔵庫に保存するときは、汁が他の食品にかからないよう容器に入れてフタやラップをする
- 卵を割ったらすぐに使う
やっつける
- 生の卵・肉・魚介類など加熱が必要な食品は、中心まで十分に加熱する
- 生の卵・肉・魚介類に使った調理器具は、使い終わったらすぐに洗い、熱湯をかけて消毒する
まとめ:菌やウイルスによって期間はさまざま
食中毒の潜伏期間と症状は原因となる病原体や摂取した食品によって大きく異なります。農林水産省の公式情報によると、肉類、魚介類、野菜・果物などの食品別に特徴があり、それぞれに適した予防方法があります。
症状が出るまでの潜伏期間は皆様気になるところですが、食中毒の場合、食後すぐに症状が出るものもあれば、数日後に症状が現れるものもあります。体調不良が続く場合は、数日前に食べたものも思い出して医師に相談することが重要です。
日常の食生活では、食中毒予防の3原則「つけない」「増やさない」「やっつける」を実践し、安全な食生活を心がけましょう。
よくある質問
-
食中毒は、食べてから何時間後に症状が出ますか?
症状が出るまでの時間は、食中毒菌の種類によって変わり、食べた直後にでるものから、1週間以上かかるものまであります。
症状が出たら自己判断せず、病院を受診しましょう。 -
食中毒を防ぐにはどうしたらいいですか?
予防には、「つけない」「ふやさない」「やっつける」が鉄則です。特に生肉などは中までしっかり加熱をしましょう。
また、包丁やまな板は生野菜などの加熱しない食品を先に切り、生の肉は後で切るなどの工夫も有効です。おにぎりは素手で触らないというもの有効です。また温度管理も心掛けましょう。
参考文献
- 厚生労働省.食中毒(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.食中毒をおこす細菌・ウイルス・寄生虫図鑑(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.サルモネラ(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.カンピロバクター(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.腸管出血性大腸菌(O157、O111など)(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.腸炎ビブリオ(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.アニサキス(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.ノロウイルス(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.黄色ブドウ球菌(2025年5月23日 閲覧)
- 農林水産省.ウェルシュ菌
著者のプロフィール

-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!
コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証
コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性
コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。







