考えてみたい「赤ちゃんの腸内環境」
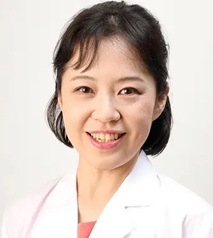
(この記事は2017年当時のことを書いています)
「菌活」という言葉が近年ブームのようです。
腸内環境を整えて、健康を維持したいと思いますよね。
しかし、赤ちゃんにとってもこれがいえるのでしょうか?
赤ちゃんの腸について考えてみましょう。
赤ちゃんの腸内環境と常在菌
お母さんの胎内にいる時は、赤ちゃんの腸内も無菌です。
生後最初の便はほぼ無菌ですが、次から大便の中に、大腸菌などが出てきます。
母乳やミルクを飲めば、次第に細菌数は増加していきます。
生後1日目には、ほとんどの新生児の糞便内に下記のような菌がでてきます。
- 大腸菌
- 腸球菌
- 乳酸桿菌
- クロストリジウム
- ブドウ球菌
などがでてきます。
生後数日たつと、ビフィズス菌が出現しはじめます。
はじめに出現した大腸菌、腸球菌、クロストリジウムなどは徐々に減少していきます。
生後5~7日目ごろから腸内細菌の大部分をビフィズス菌が占めるようになり、
7日目にはほぼビフィズス菌で占められたまま安定します。
つまり、授乳期の赤ちゃんの腸内はほとんどはビフィズス菌なのです。
腸内環境はいつ変化する?
赤ちゃんの腸内環境は、離乳食をとり始めたころから、徐々に変化していきます。バクテロイデス、ユウバクテリウム、嫌気性レンサ球菌などの嫌気性菌群が増加して、大腸菌、腸球菌が減少します。
また、ビフィズス菌の菌の種類も、赤ちゃん特有であるB.infantis、B.breveが消失していき、成人と同じのビフィズス菌の種類であるB.adolescentis、B.longumが宿ってきます。
離乳食をはじめると、便のにおいや形もかわってきますが、その1つの原因は菌叢の変化もあるのです。
離乳食だけではなく、腸内環境の変化は生活習慣の乱れによるストレスなどによっても変化があるといわれています。
他にも病気にかかったり、薬を飲んだりすることでも変わってきます。目にみえない部分だけに気になるところです。
腸内環境が気になったら

離乳食が始まって、腸内環境が気になったら、ヨーグルトなどの発酵食品を適度に食事にとりいれていくといいでしょう。
幼児期になるとおやつも大切な1食になります。おやつではなく、「補食」と呼ぶほど食事と同じ役目があります。
まとめ:腸内環境を意識した食生活
このような時間に上手にヨーグルトを取り入れるといいでしょう。
我が家では必ず朝にヨーグルトとフルーツを取り入れるようにしています。
お昼は学校で、夜はとりあわせが難しいので朝になってしまうというのが理由です。
おにぎりやみそ汁とヨーグルトというのも我が家では普通の朝ごはんです。
ちょっと気持ち悪い取り合わせでごめんなさい。おみそも発酵食品なのでそれだけでもいいのですし、本来なら発酵させた漬物があればいいのでしょうが、糠漬けをつくっていないので、ついこのようにしてしまっています。
参考資料
・腸内菌叢研究の歩み 光岡知足
・森永乳業「赤ちゃんのビフィズス」
・東京科学大学「ビフィズス菌が優勢になる乳児の腸内フローラ形成機構を解明―母乳に含まれるオリゴ糖の主要成分の利用がカギ」2016年6月30日
著者のプロフィール

-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!
コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証
コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性
コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。







