有機野菜(オーガニック)は体にいい?栄養・残留農薬・環境から考える
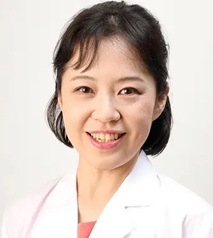
「有機野菜は体にいい」「オーガニックは健康的」──スーパーやネット通販で目にする有機野菜やオーガニック食品。価格は高めですが、健康や安全性を考えて選んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、本当に有機野菜は「体にいい」と科学的に言えるのでしょうか?
有機野菜やオーガニックという言葉の定義、栄養価の差や、残留農薬の危険性、そして環境への影響について、管理栄養士が解説します。
結論を先にお伝えすると下記3点です。
- 「有機野菜だから体にいい」や「栄養価が高い」や「おいしい」とは断定できない
- 有機野菜は土壌環境や生物多様性へのメリットは考えられる
- 選択は個人の価値観次第
有機野菜・オーガニックとは?【農林水産省の定義】
有機農業の法的定義
日本では、平成18年に制定された「有機農業の推進に関する法律」において、有機農業を以下のように定義しています1)。
有機農業の3つの原則:
- 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
- 遺伝子組換え技術を利用しない
- 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
では、「有機」と名乗れるのは、どのようなものなのでしょうか。
有機JAS認証制度とは
日本で「有機」「オーガニック」と表示できるのは、有機JAS認証を取得した農産物のみです。
有機JASマークの取得条件は、下記のとおりとなります。
- 種まき・植付け前2年以上、化学肥料や化学合成農薬を使用していない農地で栽培
- 周辺から禁止資材が飛来・流入しないよう措置を講じる
- 遺伝子組換え技術や放射線照射を行わない
- 登録認証機関による検査・認証を受ける
有機JASマークがない野菜に「有機」「オーガニック」と表示することは法律で禁止されています2)。
よくわからなくなりました。
でも、少なくとも
有機JASをとっているものは「無農薬ですよね?」
よくわからなくなりました。
でも、少なくとも
有機JASをとっているものは「無農薬ですよね?」

有機JASをとっていても、農薬は使っているものもありますよ。
有機JASをとっていても、農薬は使っているものもありますよ。

管理栄養士
原則として、有機JASでは化学的に合成された農薬や肥料の使用を禁止していますが、
化学的に合成されておらず、使用が認められている農薬もあります2)。
つまり、「無農薬」という言葉と「有機栽培・有機JAS」の言葉は異なります。有機JAS認定のものでも使える農薬はあるのです。
しかし、混同されて使われることも多く、結果として表示があいまいになりやすいです。
では、反対に、無農薬のものは有機といえるかというと、有機JAS認定していないものは基本的には有機とは名乗れません。
【関連記事】ベビーフードは無添加やオーガニック、有機野菜がいい?
【関連記事】脂質の種類などについて記載あり:オイルファーストはからだによい?
「有機」と「オーガニック」の表示規制
日本の法律(JAS法、食品表示基準)では、有機JAS認証を取得していない農産物に以下の表示を使うことを禁止しています2)。
- 「有機○○」
- 「オーガニック○○」
- 「organic」
- これらと紛らわしい表示
つまり、消費者庁・農林水産省は、これらの表示を実質的に同等として規制していることになります。
輸入品・他国制度との関係
しかし、輸入品や海外の「オーガニック」表示には、国ごとに認証基準・用語の使い方が異なります。例えば、海外制度で「organic」と表示している場合、そのまま日本の有機JAS表示には使えるとは限りません。そのため“有機相当”として別表示がされることがあります。
例えば、海外●●のオーガニック基準認証 などです。
一般的な栽培方法:慣行栽培
慣行栽培とは、化学肥料や化学合成農薬を使用する一般的な栽培方法です。
ただし、これは「農薬漬け」という意味ではなく、法律で認められた範囲で適正に使用しており、国の残留農薬基準を十分に満たした、安全性の確認された栽培方法です。
また、「特別栽培農産物」という区分もあり、これは化学肥料・農薬を通常の50%以下に減らした栽培方法であり、有機JASとは別の制度になります。

有機野菜は「体にいい」と言えるのか?
さて、本題にうつります。「有機野菜は栄養価が高く体にいい」という説は、科学的に正しいのか一緒に考えてみましょう。
栄養価に大きな違いはない
ケンブリッジ大学のメタアナリシス
イギリスの研究(2014年)では、有機農産物と慣行栽培の栄養成分を比較した343の査読付き論文を分析し、下記のような発表をしています4)。
- 主要栄養素(ビタミン、ミネラル等)に統計的な有意差は認められなかった
- 一部の抗酸化物質(ポリフェノール類)は、有機栽培で18-69%高い傾向がみられた
英国食品基準庁(FSA)
「有機食品の病気予防効果や健康上の優位性を示す十分な証拠はない」と発表しています5)。
日本における、有機栽培の栄養価と成分表との違いの論文
2009年の島村らの研究では、有機栽培と、成分表の数値を比べていますが、これらでは栄養の有意差はみられませんでした。
最後には「一般に有機農産物は,慣行栽培されたものに比べ,健康に良いと考えられているが、本研究の結果から,その考え方を科学的に証明する結果は得られなかった」と締めくくっています。
他にも、研究はありますが、いずれも、有意差はみられませんでした6)。

管理栄養士
つまり、「有機野菜は栄養価が高いから体にいい」とは科学的に断定できません。
残留農薬の安全性
次に、「農薬が心配だから有機野菜を選ぶ」という方も多いでしょう。
日本では、厚生労働省が食品衛生法に基づき、すべての農薬について残留基準を設定し、基準を超える食品の流通は禁止しています。

管理栄養士
令和5年度には、50,000検体のうち、残留農薬基準を超えていたものは0.1%未満であり、違反事例のほとんどは輸入食品でした。
つまり、日本の慣行栽培野菜は残留農薬の安全基準をほぼ100%満たしています。
どちらも問題ない
つまり、一般的な慣行栽培と、有機栽培の有意差はなく、どちらも安全です
- 慣行栽培の野菜も厳格な残留農薬基準をクリアしており、安全性に問題はない
- 「農薬が怖いから有機野菜」という選択は過度な心配の可能性
あくまでも楽しく選ぶ選択肢の1つとして考えてみませんか?
あくまでも楽しく選ぶ選択肢の1つとして考えてみませんか?

管理栄養士
有機農業のメリット?
ここまで見てきたように、「体にいい」という直接的な健康効果は科学的に証明されていません。
しかし、有機農業には環境メリットがあるかもしれません。
例えば、農薬などをなるべく減らすことで、土壌有機物が増加したり、微生物の種類が増えたりすることも考えられるかもしれません。これは有機だけに起きることではなく、土壌を豊かに肥料などを考えても同じことは起きえますが、有機農業はより自然に行うことができるともいえるでしょう。
例えば、近くに虫がいるとか、そういうことで、私たちの生態系を一部維持していくことは人間社会と自然界が共存する上では大切になることもあります。
夏休みに近所の田んぼの用水路にはたくさんのタナゴが泳いでいて、よく観察していました。そんな暮らしもとても素敵だなと今も思います。
夏休みに近所の田んぼの用水路にはたくさんのタナゴが泳いでいて、よく観察していました。そんな暮らしもとても素敵だなと今も思います。

管理栄養士
コーデックス委員会も「有機農業は、生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理システムである」としています10)。
まとめ
つまり、国内外様々な論文をみても、有機農法の野菜(有機野菜)が栄養価が高い、健康に良いなどを結論付けているものは見つかりませんでした。
また、残留農薬については厳しい基準があるので、有機野菜ではないものであっても安全であることが証明されています。
「有機野菜使用」「無農薬」などはさまざまな商品を売るときにつけられたりもしますが、基本的には有機JASを受けていない限りは使用することができない言葉になっています。
有機やオーガニックだから体に良いということはわかりませんが、生物の多様性の観点から利点があるのではないかというのがCODEXはじめ世界的な見方となります。
選び方は自由、どちらがいい、どちらが悪いということはありません。
有機か慣行かにこだわりすぎるよりも、まずは野菜をしっかり食べる習慣を大切にしましょう。
ただしく食材を選んでいけるようになりたいですね!
メールマガジンのご案内
妊娠中と子どもの食事について、月1回ほどお届けしています。
よくあるご質問
-
有機野菜を選んだほうがいいですか?
個人の価値観次第です。環境保全を意識するなら有機野菜を選ぶこともいいでしょう。安全性や栄養面などであれば、有機ではない慣行栽培でも同じです。
環境保全を重視する方→有機野菜を選ぶのも価値あるでしょう
栄養・安全性を重視する方→有機だから安全などはありません。慣行栽培でも十分安全なのでどちらでもOKです -
野菜の栄養は、どのように変わりますか?やはり有機野菜や農薬少ないほうが栄養は高いですか?
細かいことを言えば、野菜は季節・土壌の栄養・日照時間などによってさまざまな面で栄養は多少は異なります。また、収穫してから食べるまでの時間や保存条件によっても栄養は変わります。
しかし、それらを細かく計算する必要はありませんし、一般的にできるすべはありません。
気になる場合は、
・野菜の種類を多様にする
・新鮮なものを選ぶ
・十分な量を食べる(大人は1日350g以上)
・季節の野菜を取り入れる
などを意識してみましょう。 -
「有機野菜」」と「無農薬野菜」との違いは?
A. 法律上「無農薬」という表示は禁止されています。
・「無農薬」は曖昧で誤解を招くため
・公的認証があるのは「有機JAS」のみ
・ネット販売などで「無農薬」または「無農薬野菜使用」と表示している場合は違法に当たる可能性が高いです -
子どもには有機野菜を食べさせるべき?
いいえ。どちらでも構いません。
まず、日本の残留農薬基準は乳幼児の安全性も考慮されていますので、
一般的に売られている野菜は残留農薬基準を満たしています。
基本的に普通の慣行栽培の野菜でも安全性に問題は全くありません。
有機野菜を選んでいただくのも構いませんが、「有機野菜しか食べさせない」とこだわると、野菜の種類などが偏ることがあるかもしれません。
有機野菜でも、普通の慣行栽培野菜でも構いませんので「さまざまな種類の野菜をしっかり食べる」ことを優先しましょう。 -
有機野菜を選んだ方がアレルギーや発達障害になりにくいですか?
いいえ。そのようなことはありません。
さまざまな病気の原因はまだ未知なこともあるために、見えない恐怖とくっつけてしまったりしがちですが、そのような発表をみつけることはできませんでした。
アレルギーに関しては、しっかりスキンケアをすること、病院にかかって医師にみてもらうことです。
偏らずいろいろなものを食べていけるといいですね。
【関連記事】ベビーフードは無添加やオーガニック、有機野菜がいい?
【関連記事】マクドナルドのポテトやナゲット、バーガーのカロリー&塩分|管理栄養士解説
参考文献
- 農林水産省.有機農業関連情報(2025年10月27日 閲覧)
- 農林水産省.有機食品の検査認証制度について(2025年10月27日 閲覧)
- 農林水産省.有機食品の検査認証制度(2025年10月30日 閲覧)
- Barański, M., Średnicka-Tober, D., Volakakis, N., et al.. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition . 2014年7月;112(5):794-811(2025年10月27日 閲覧)
- BBCニュース.Organic 'has no health benefits'(2025年10月30日 閲覧)
- 食品安全委員会.英国食品規準庁(FSA)、有機食品に関する外部委託調査結果を公表(2025年10月30日 閲覧)
- 島村裕子ら. 有機野菜と慣行野菜の微生物の分布ならびにミネラル・ビタミン含量の比較. 日本家政学会誌 . ;Vol.60 No.5: 491-498(2025年10月30日 閲覧)
- 辻村卓ら. 「栽培条件(有機栽培と慣行栽培)の違いによる野菜栄養成分の比較[I]. ビタミン. ;Vol. 79 No. 10:497-502(2025年10月30日 閲覧)
- 厚生労働省.食品中の残留農薬等(2025年10月27日 閲覧)
- Codex.有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン(CXG 321999) (2025年10月30日 閲覧)
著者のプロフィール

-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!
コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証
コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性
コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?
- カテゴリー
- コラム
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。







