化学調味料 無添加とは?知っておきたい消費者庁のガイド
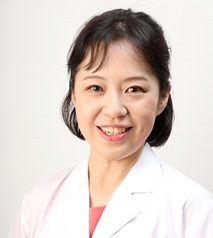
市販品などを購入する際、「化学調味料不使用」という表示などを見たことがありますか?
このような表現があったら、「身体によさそう」と勘違いしてしまったりしていませんか?
実は「化学調味料 不使用」などは表記はしてはいけないのです。
今回は、消費者庁が発表したガイドラインに基づき、
食品添加物の不使用表示に関する考え方を管理栄養士がお伝えしますね。
化学調味料とは
化学調味料とは、現在は使わない、使ってはいけない言葉になっています。
どういうことですか?
どういうことですか?

実は現在では「使ってはいけない言葉」ですが、
一般的に言われているものがどういうものなのかから解説しますね。
実は現在では「使ってはいけない言葉」ですが、
一般的に言われているものがどういうものなのかから解説しますね。

管理栄養士
もし、使われているとしたら、化学調味料とは、特に「うま味」を使う調味料などのことを指していると思われます。
うま味調味料の中で有名なのは、グルタミン酸ナトリウムです。(他にもあります)
うま味調味料(化学調味料)の起源と歴史的変遷
- 1908年 池田菊苗博士が、昆布だしのうま味成分がグルタミン酸であることを発見1)
- 1909年 うま味調味料「味の素®」を製品化1)
- 1937年 別企業が会社設立時の事業内容を「化学調味料製造」と記載2)
- 1950‐60年代 NHKの料理番組で、公共放送の立場上製品名で呼べないため、「化学調味料」として紹介3)
- 1960年 食品衛生法に基づき、グルタミン酸ナトリウムが安全と認められる。
- 1985年以降 呼称「うま味調味料」となる3)
びっくりです!
びっくりです!

そのような商品を目にしたりしますが、正式名称ではないのです。
そのような商品を目にしたりしますが、正式名称ではないのです。

管理栄養士
マーケティング要素の強い「化学調味料」という言葉
このように、現在では「化学調味料」という表現は使用されていません。
代わりに「うま味調味料」が正しい表現となります。
しかし、依然として「化学調味料不使用」といった曖昧な表現が見受けられますよね。
特に、離乳食や幼児食などに多く見られる気がします。
身体によくないようなイメージの言葉を使い、不使用と表記することで
消費者心理をついていますよね。
からだに良い気がして、買ってしまいます。
からだに良い気がして、買ってしまいます。

少しだけ知っておくと、食事の選び方が変わったり、表記に騙されないようになるので、
もし興味があったら、もう少し一緒に勉強していきましょう!
少しだけ知っておくと、食事の選び方が変わったり、表記に騙されないようになるので、
もし興味があったら、もう少し一緒に勉強していきましょう!

管理栄養士

なぜ「不使用」や「無添加」といった表記が広まったのか
「化学調味料不使用」や「無添加」という表示が広まってしまった背景には、
消費者の添加物に対する不安を解消したいという心理を反映した結果ではないでしょうか。
自然由来や無添加をアピールすると、消費者が動くというムーブを作ってしまうと、
メーカーがそれらを謳い文句(キャッチコピー)にしていくという流れに繋がったと考えられます。
必ずしも科学的根拠や法的基準に基づいているわけではない点が、消費者との製造現場、イメージや実情のズレが生じてしまっているかもしれませんね?
必ずしも科学的根拠や法的基準に基づいているわけではない点が、消費者との製造現場、イメージや実情のズレが生じてしまっているかもしれませんね?

管理栄養士
「化学調味料不使用」表示への期待と誤解
「化学調味料不使用」といった表示は、健康的で自然な食品を連想してしまいますよね。
ですが、実際には「化学調味料不使用」や「無添加」と書かれていても、別の食品添加物が含まれている場合があり、表示が持つ意味を正確に理解できないケースがあります。
例えば、「うま味調味料」を使わずとも、酵母エキスやたん白加水分解物といった代替原料が使用されていることもあります。
これらが、良い悪いという話ではなく、イメージで捉えてはいけないということなのです。
このように、こうしたイメージ先行の「化学調味料」「無添加」などの表示で間違えた期待を与えないために、消費者庁がガイドラインをだしました。
消費者庁、食品添加物の不必要表示のガイドライン
消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」4)を2022年に定めました。
このガイドラインでは、消費者が誤解しないように注意を促しています。
ガイドラインの10類型
このガイドラインは10の類型にわかれています4)。
類型1:単なる「無添加」の表示
消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」4)
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示 2
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ れていないことが確認できない)食品への表示
類型10:過度に強調された表示
このガイドラインでは、以下の点が強調されています
1.種別なしの無添加表記の禁止
特定の添加物名を明記せずに「無添加」とすることや、あいまいな表現を使用することを禁止しています。これは、「類型1:単なる無添加の表示」に該当します。
ガイドラインで禁止されている表現と代替案
×「無添加」「無添加食品」
→なにが無添加なのかわからないので、NG。正しくは「甘味料無添加」など
2.規定以外の用語使用の禁止(化学調味料、人工甘味料など)
これは、「類型2食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 」に該当します。
食品表示基準において規定されていない用語は認められていません。
例えば、化学、人工、合成、天然などです。
つまり、「化学調味料」や「人工甘味料」「合成着色料」という表現は、できません。
代わりに「うま味調味料」や「甘味料」といった正式、なおかつ具体的な表現を使用すること
とされています。
ガイドラインで禁止されている表現と代替案
×「化学調味料無添加」
→化学調味料という言葉は正式名称ではないのでNG。正しくは「うま味調味料無添加」など
けっこうインスタで見かけますけど…
けっこうインスタで見かけますけど…

食品添加物不使用表示の移行期間
このガイドラインは2022年3月に策定されて、2年間が移行期間です。
つまり、2024年4月1日から、このガイドラインの内容が完全に義務化されます。
現在、曖昧な表現や具体的な添加物の内容を明記しない表示は違反となります。
今もし見かけたら、食品表示基準9条5)の違反となる可能性がありますね
今もし見かけたら、食品表示基準9条5)の違反となる可能性がありますね

管理栄養士

まとめ:「無添加」と「不使用」に惑わされない食品選びを
信頼できる食品を選ぶために、
商品パッケージのラベル表示をしっかりと確認することは、大切です。
例えば「化学調味料無添加」や「合成添加物不使用」等の表記に
惑わされないでいたいものです。
具体的に添加物が、どのように使用されているのかを考えましょう。
添加物を使っている目的はなぜか等を原材料表示から読み取るようにするといいですね。
無添加だから安全とは限りません。腐敗や劣化から避けるためには必要なこともあります。
宣伝文句に惑わされず、具体的な成分や原材料を確認する視点を持てるといいですね。
食品メーカーの皆様へ 無添加表記見直しのお願い
食品メーカーにおかれましては、消費者が誤認しないような表記を心がけましょう。
育児中の保護者は、小さい命を抱える不安をかかえています。
また、赤ちゃんのお世話が忙しく、なかなか深く考える時間もとれないのが現状です。
消費者が安心して食品を選べる環境を作ってくださると嬉しいです。
「無添加だから安全」や
「赤ちゃんの健康を考えた無添加」などは
上記類型7や8に該当します。
食品表示基準第9条5)の違反になる可能性があります4)。
食品基準を守った、透明性のある表記をお願いします。
参考文献
2)大蔵省印刷局,官報 3058号(昭和12年3月16日),(国立国会図書館デジタルコレクション 2025年3月21日閲覧)
3)味の素>味の素®の原材料は何?製法は?安全なの?(2025年3月21日閲覧)
4)消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」令和4年3月30日(2025年3月21日閲覧)
5)消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ:無添加表示が変わります」(2025年3月21日閲覧)
著者のプロフィール
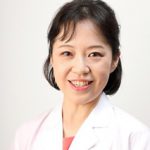
-
一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
記事
- 2025年4月18日コラム卵焼き器でレトルト食品を温めるのは要注意!理由と解説
- 2025年4月17日コラム離乳食のツナ缶:種類はノンオイル(水煮)?いつからOK?
- 2025年4月1日コラム賞味期限と消費期限の違いの解説と歴史的経緯
- 2025年3月29日コラム管理栄養士国家試験 合格率低下と平均年収からの考察
お問い合わせ
母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。
当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。



